眠ったはずなのに朝起きても疲れが残っている。 そんな朝を迎えたことはありませんか。 私も同じ経験があります。夜遅くまでスマホを眺めて布団に入り、目を閉じても頭が冴えて眠れない。 ようやく眠っても何度も目が覚めてしまい、翌朝は体が重たい。 出勤しても仕事に集中できず、ちょっとしたことで気持ちが乱れる。 眠ったはずなのに休めていない――その繰り返しが自分をじわじわと追い詰めていたのです。
そのとき気づきました。 必要なのは「長く眠ること」ではなく睡眠の質を上げること。 それは体の健康だけでなく心の穏やかさ、そして暮らし全体の充実に直結するのです。
眠りの浅さが教えてくれたこと
ある時期、私は夜遅くまでスマホを手放せませんでした。 布団に入ってからも画面を開き、気づけば深夜一時。 翌朝はアラームが鳴っても起き上がれず、頭はぼんやり。 会議では話が頭に入らず、午後には強い眠気に襲われる。 眠りが浅いことが、日常を大きく揺らしていたのです。
後になって知ったのですが、スマホから出るブルーライトは脳を覚醒させて眠りを浅くするといいます。 つまり「眠れない原因は自分の習慣にあった」ということ。 小さな積み重ねが翌日の心と体に大きく響いていたのだと気づかされました。
睡眠と病気の関わり
眠れない状態を「疲れているだけ」と見過ごすのは危険です。 慢性的な睡眠不足は高血圧や糖尿病、肥満や心疾患と結びつきやすいといわれています。 心の不調にも影響し、うつ病や不安障害の背景に眠りの問題が潜んでいる場合もあります。
厚生労働省の調査では、日本人の平均睡眠時間は世界的に見ても短い水準とのこと。 「眠れていない」という悩みは多くの人に共通するテーマでしょう。 さらに、いびきの裏に「睡眠時無呼吸症候群」が隠れていることもあります。 放置すると心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる病気で、専門的な治療が必要になることもあるのです。
だからこそ睡眠の質を上げることは、体と心を整えるだけでなく、病気を防ぐ第一歩でもあるのです。
睡眠の質を上げるためにできること
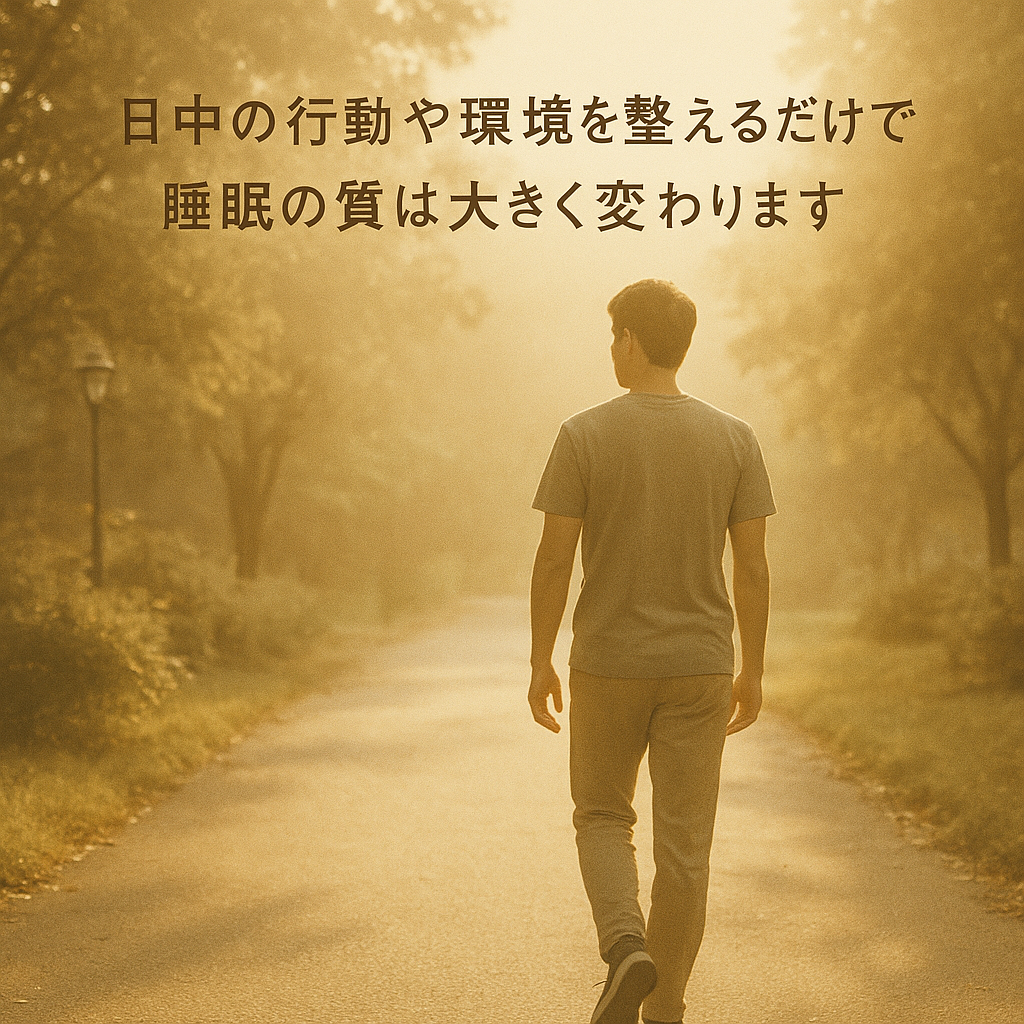
寝る前の習慣を変える
私が最初に取り入れたのは、寝る一時間前にスマホを手放すことでした。 照明を落とし、温かい飲み物を用意して本を開く。 それだけで不思議と眠気が訪れるようになります。 熱すぎないお風呂に浸かるのも効果的でした。 体温が一度上がり、その後ゆるやかに下がっていく流れが眠気を誘うのです。
環境を整える
眠りやすい環境づくりは思っている以上に効果があります。 夏は冷やしすぎないようにエアコンを調整し、冬は寝具を工夫して暖かさを保つ。 湿度を五〇%前後にすると夜中に喉が渇いて目覚めることが減りました。 枕を替えてみたら呼吸が楽になり、眠りの深さも変わった気がします。 環境を整えることは翌日の自分を支える基盤になるのです。
日中の行動を見直す
朝はカーテンを開けて光を浴びる。 夕方に軽く散歩をする。 それだけでも体内時計は整い、夜の眠りは深くなります。 私は歩くだけの運動を続けていますが、それでも気分が落ち着き、夜は眠りやすくなりました。 運動が苦手な人でもできる小さな一歩です。
心を落ち着ける
心配事を抱えたまま布団に入ると、どうしても眠りは浅くなります。 私は布団の中でゆっくりと呼吸することを習慣にしました。 吸って、吐いてを繰り返すと自然に心が落ち着いていきます。 ラベンダーの香りを取り入れると安心感が増し、深い眠りを後押ししてくれるようでした。
実際に感じた変化
こうした工夫を続けるうちに、朝の目覚めは大きく変わっていきました。 以前は布団から出るのがつらく、気持ちも沈んでいたのに、今では目覚ましが鳴る前に自然と目が覚めることさえあります。 頭の重さが減り、日中も集中できる時間が増えました。 人との会話も前より楽しめるようになり、自分自身が軽やかになったように感じます。
「眠ること」は当たり前のようでいて、暮らしの質を大きく左右するもの。 睡眠の質を上げることは、人生の質を上げることにつながるのだと実感しています。
まとめ――今日からできる一歩
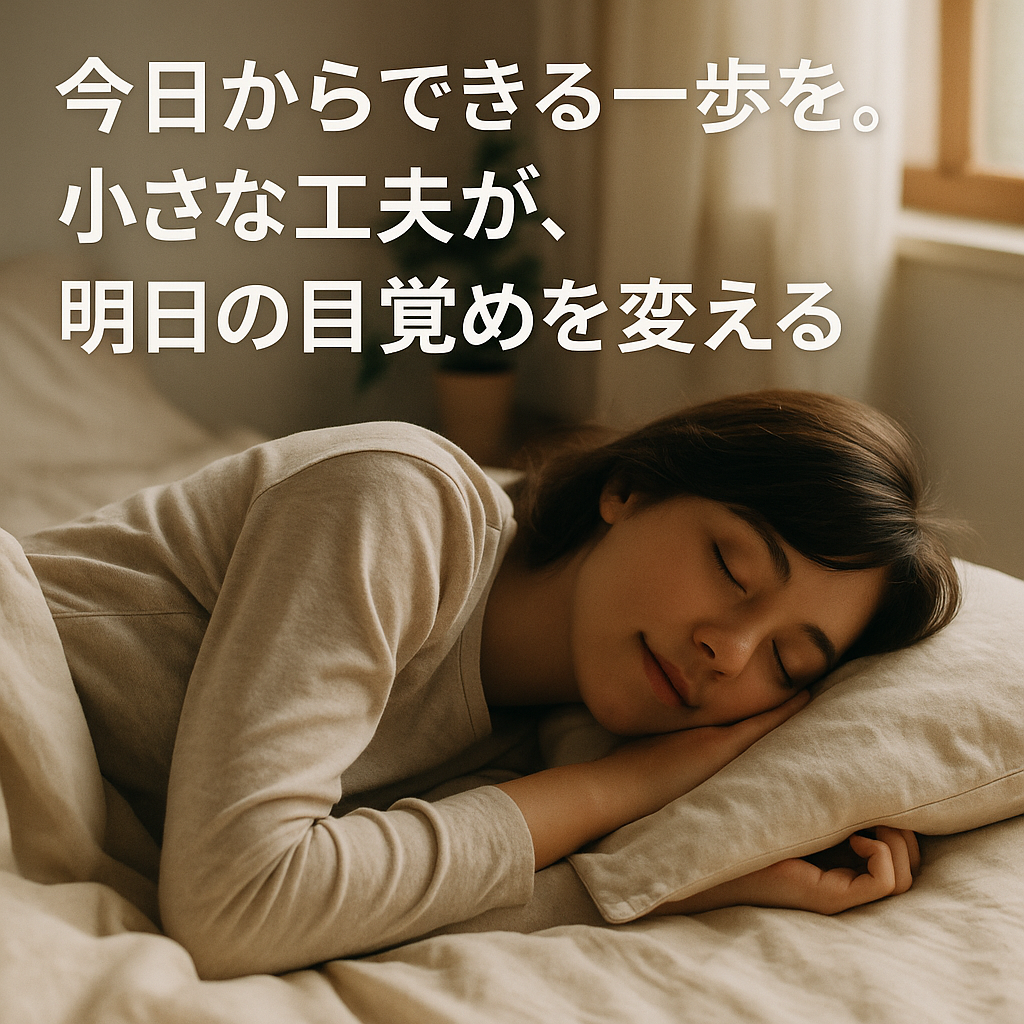
睡眠は休むだけの時間ではなく、体と心を回復させる大切な営みです。 その力を活かすには質を整えることが欠かせません。 大きなことをしなくても大丈夫。 寝る前にスマホを手放す。 照明を落とす。 深呼吸をする。 どれか一つでもいいのです。 きっと明日の朝は少し違っているはずです。
あなたにとって心地よい眠りを見つけることは、未来の自分を守ることにつながります。 今日から小さな習慣を選び、眠りを整える一歩を踏み出してみませんか。

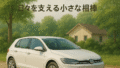
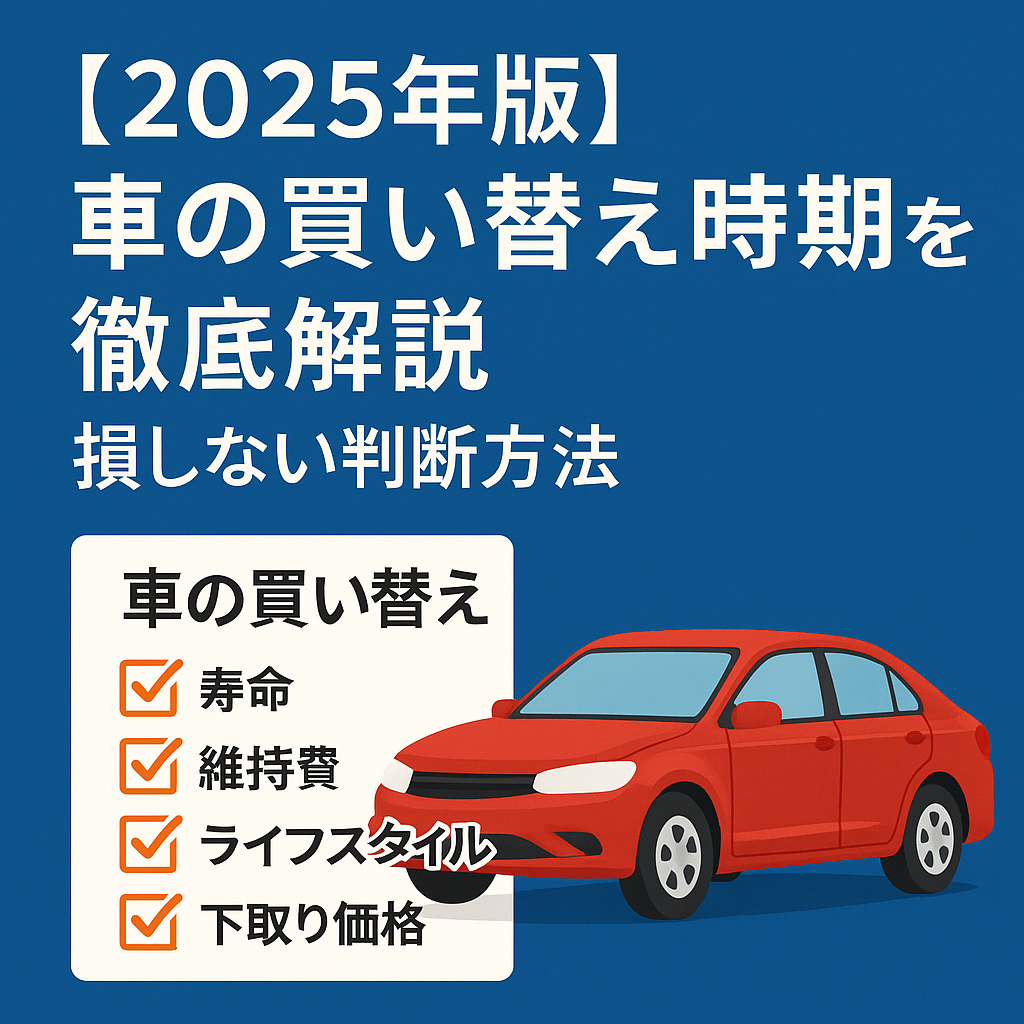
コメント